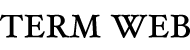1歳半なのに絵本の指差しをしない!指差しは子供の成長に必要
2018/09/28

赤ちゃんが絵本などに指差しをすることができるかどうかは、赤ちゃんの1歳半検診の項目でもあります。これは、絵本などを見て指差しをできるかどうかが、赤ちゃんの成長や発達を判断するときの大切なポイントになるからです。
でも、赤ちゃんの指差しが大切なのはどうしてなのでしょうか?1歳半になっても指差しをしないのはおかしい?
そこで今回は、赤ちゃんの指差しが大切な理由や指差しをしない時の練習方法・年齢別の指差しの意味についてお伝えします。
スポンサーリンク
こんな記事もよく読まれています
-

-
公園のトイレは怖いこともあるので防犯対策をしっかりしましょう
公園のトイレは苦手、怖いという子どもは多いと思います。なぜ、...
-

-
顔が違う?写真の自分と鏡の自分の顔が違う!鏡の方が美人な理由
写真に映った自分の顔と鏡に映った自分の顔が違う事に驚いた経験...
-

-
セキセイインコはおしゃべり上手だがメスは苦手?教えるコツとは
セキセイインコはおしゃべりをしますが、メスは苦手だと言われて...
-

-
猫の保健所への持ち込みを減らすメリットやあなたができること
猫が保健所に持ち込みをされるのは、飼い主が事情により飼うこと...
-

-
洗濯機の排水トラップの外し方と掃除方法!悪臭の元をさっぱり
洗濯機の排水トラップの掃除をしたことがありますか?洗濯機から...
-

-
猫の父親は子育てしない!母猫の役割や猫の子育て期間について
猫の父親は子育てには普通参加しません。猫の世界では、子育ては...
-

-
フクロモモンガのケージを自作する場合のポイントと注意点
フクロモモンガを飼育している方の多くは、ケージを自作していま...
-

-
卵を割るために握力な握力と簡単に割る方法を解説します
りんごを片手で割る映像を見ると、卵も握力があれば割ることがで...
-

-
畳のいろいろな素材と種類の特徴!素材の違いを比較
和室に必要な畳にはいろいろな素材の物があります。その種類は多...
-

-
ハンドメイドのオーダーメイド販売のやり方とポイント
ハンドメイドのオーダーメイド販売のやり方について迷ったことな...
-

-
大学の勉強は意味ないと悩んでいる人へ。大学で勉強する意味
「大学で勉強する意味ない」「もう大学を辞めたい」と悩んでいま...
-

-
人の名前が覚えられない!覚えられない理由と覚えるコツ
人の名前が覚えられないのはなぜでしょう。 大きく分けると理...
-

-
壁紙の修復方法!剥がれを自分で直す方法とキレイに仕上げるコツ
壁紙の剥がれは早めに対処するのがおすすめです。そのうち直そう...
-

-
季節のおもちゃで魚を製作!1歳児でも作れる魚アイデア集
雨の日などは外に出ることも敬遠しがち。でもお家のおもちゃで遊...
-

-
試験に合格する夢を見た時の夢占い!夢の内容で見る未来の暗示
試験に合格する夢を見た時、その夢にはどんな夢占いの意味がある...
-

-
女性のベスト着こなし術・おしゃれ上級者になれるベストのコーデ
ベストをファッションに取り入れて、おしゃれな着こなしがしたい...
-

-
猫の鳴き声『ニャー』ではなく『んーんー』この鳴き声の意味とは
猫の鳴き声といえば『ニャー』ですが、この『ニャー』は猫同士の...
-

-
ヒョウモントカゲモドキは脱皮した皮を食べる?脱皮について
ヒョウモントカゲモドキが脱皮の皮を食べるという話を聞いたこと...
-

-
音の振動を塩を使って調べる自由研究!実験の手順とまとめ方
自由研究で音と振動について実験をしてみたいという場合には塩を...
-

-
カクレクマノミがイソギンチャクに入らない。気長に待とう
カクレクマノミとイソギンチャクの戯れを見たい。なのに、カクレ...
スポンサーリンク
この記事の目次
1歳半の子供が絵本に指差ししない!子供の指差しって大切?
まだ言葉を上手に話せない赤ちゃんが、「あ~」や「う~」といいながら何かを指さして教えてくれることがあります。
この仕草のことを「指差し」といい、これは何か興味をひかれたものや、欲求のあるものに指をさして示すという行動のことです。
この指差しは、みんなが同じではなく、人差し指で示したり、手全体を使って示すこともあります。
まだ、言葉によるコミュニケーションがうまくとれない子供にとって、この「指差し」には大きな意味があります。
ただ泣いたり、寝ていた赤ちゃん時代から、徐々に何かに興味を持ち始めたという成長を感じる行動とも言えるでしょう。
赤ちゃんの頃は、ママと目が合うと笑ったりなど、赤ちゃんとママの2人だけの関係性であったものが、この指差しで、自分と相手、そしてもうひとつという初めて3者間の関係が築けるようになったということになります。
1歳半で絵本の指差しをしないのはおかしいの?
各市町村で赤ちゃんの1歳半健診というものをどの赤ちゃんも受けますが、この健診では、おもに身体の発達状態と、精神発達の度合いを見ます。
赤ちゃんの様子だけではなく、医師や保健師に保護者の心配ごとを相談できるという大切な場でもあります。
各市町村ごとで、実施する内容に多少違いはありますが、積み木をちゃんと重ねられるかを見たり、単語をいくつか言えるかを確認したり、そしてこの「指差し」が出来るかを見るということが一般的です。
1歳半健診で、指差しができない場合は、「要観察」もしくは「要指導」になる場合が多いようです。
他のチェック項目はきちんと出来ていて、指差しだけができないなどの場合は、保健師さんが総合的に見て判断してくれるので、そんなに心配することがないと思われますが、指差しをまったくしなくて心配の場合は、1歳半健診の前に、小児科などで相談するという方法もあります。
健診の場の子供の様子以外にも、家庭での子供の様子を聞かれる場合がありますので、事前に話す準備をしておくと良いでしょう。
1歳半になっても絵本の指差しをしないときは気軽に相談を!
指差しは、色々なものに興味が出始める1歳前後から行うようになることが多いです。
指差しの意味にも色々あり、「共有」「欲求」「応答・理解」という3つに分けられます。
- 「共有」…例えば花を見てキレイと思って、それを教えたい気持ち
- 「欲求」…おやつをとってほしい、飲み物がほしいという気持ち
- 「応答・理解」…絵本などでニンジンはどこ?という質問に対して答える気持ち
この指差しは、子供にとっては重要なコミュニケーションツールであり、1歳6ヶ月健診でも指差しができるかどうかが発達状況を確認する要素のひとつになります。
ただ、この指差しだけが発達確認の基準にはならず、あらゆる方向から総合的に判断します。
赤ちゃんが指差しをしないときの練習について
子どもが自分から指差しをしてくれない時、親としては少し心配になることもあるでしょう。
1歳を過ぎても、指差しする傾向がなく、気になるときには、ママやパパと練習してみるということもひとつの方法です。
子どもに無理強いはせず、嫌がるようなら改めるのも大切です。
子どもは常に身近な存在であるママやパパの様子を見ています。
時にはしぐさを真似ることもありますので、子どもに「○○ちゃんはここにいるね」などと話しかけながら指差したり、自分を「ママはここだよ」と指差してみるという方法で、真似を始めることもあります。
または、子どもの前におもちゃをいくつか置き、好きなおもちゃはどっち?と聞いて選ばせてみる方法や、絵本を使い、読みながら、絵を指差ししてあげるというのも有効です。
この練習は、した方が良いとかいつから始めるのが良いなどは子どもによっても変わりますので、一概にはいえません。
気になるようであれば専門の医療機関でも相談に乗ってくれますので、検討してみることをおすすめします。
赤ちゃんの年齢によっても違う指差しの意味について
指差しが始まるのは、1歳前後は一番多いですが、その中でも比較的早い時期(9ヶ月から1歳頃)にする指差しは、自分が興味があるものや好きなものに対してすることが多いです。
例えば、散歩中に見かけた犬を見つけて「ワンワンだ!」というような意味の指差しです。
車が好きな子どもであれば、大きなバスを見つけて指差しすることもあります。
1歳を過ぎる頃には、欲求も今までよりはっきりしてきますので、自分の欲しいものに対して指差しして教えることも出てきます。
そして、1歳半のあたりから、自分の見つけたものや興味のあることを周りにも知ってほしいという「共感」の指差しが出始めます。
また1歳半頃には、複数の単語を言えるようになる時期ですが、まだうまくしゃべることができない子どもでも言うことの理解は出来ていることが多いです。
この場合、ママの問いかけに対して、指差しで答えようとする子どもがいますが、これが「応答」の指差しになります。